明治大学全国校友石川大会記念 |
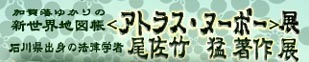 |
明治大学全国校友石川大会記念 |
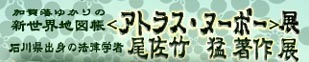 |
尾佐竹猛(おさたけ・たけき)は、加賀藩士で漢学者であり、明治維新後は石川県羽咋郡役所の役人や小学校長を勤めた尾佐竹保の長男として、明治13年1月20日に羽咋郡志賀町に生れた。大念寺新小学校(明治22年に高浜小学校と改称)を終えて、東京に遊学。
明治29年5月、明治大学の前身である明治法律学校に入学し、同32年7月に卒業した。
同年11月、19歳にして判事検事登用第1回試験に最年少者で合格し、司法官試補として東京地方裁判所詰に任用された。その後、福井地方裁判所判事、東京控訴院判事、大審院判事、帝国議会憲政史編纂所長などを歴任した。昭和3年には、「維新前後における立憲思想」で、東京帝国大学から法学博士の学位を授与されている。
昭和6年、明治大学法学部教授。同7年に、現在の文学部の前身である文科専門部が設置されると、嘱望されて部長に就任する。この要請に尾佐竹は再三固辞するが、当時の「駿台新報」は、大明治建設の大事に母校出身の尾佐竹博士としてむげに拒否する筈はなかろうし、編制委員一同も、生命をかけても受諾させねばならないと意気込んでいる、と報じた。
一方で、吉野作造に誘われて「明治文化研究会」の創設に参加、吉野死後は第二代会長。明治文化研究の第一人者としても活躍した。
早くから文筆家として知られ、22歳にして郷土の地誌『志賀瑣羅誌』を執筆、法曹の分野では、『賭博と掏摸の研究』など他に例をみないユニークなテーマでの研究をはじめ、生涯に50冊近い著書を残した。昭和21年10月1日に66歳で没するが、死後も復刻版や生前の雑誌連載をまとめた著作20余冊が刊行されるなど、今なお評価は高い。
墓は、金沢市東山の蓮覚寺にある。
*尾佐竹猛の父親が藩庁に提出した原本で、禄高、出自、履歴、先祖の系譜、4親等までの親族が書き上げられている。
*明治大学文科は明治39年に夏目漱石、上田敏を擁して発足したが、1回の卒業生を送り出しただけで廃科となった。創立50年を機に文科復活の機運が高まり、尾佐竹を委員長に編制委員会が設置され、部長にも推薦された。尾佐竹のもとに、文芸科、史学科、新聞科が置かれ、それぞれ山本有三、渡辺世祐、小野秀雄が科長に名を連ねた。
*郷土誌『志賀瑣羅誌』の執筆でもわかるように、郷土への愛着は人一倍強く、郷友会とのかかわりを深くもち続け、郷土雑誌への寄稿も数多い。
*筆名の不破志要は「ファッショ」と読む。下掲の田熊渭津子氏の調査によれば、この他に、雨花子、縦横子、活殺子、無用学博士、芦田真足(アシタマタル)、相良武雄(アイラブユウ)、倭遅通散史(イチニサンシ)、井田蛇義(イデオロギー)、甲斐元齢(カイゲンレイ)、周布佩波(ステープルファイバー)、千田世成(センデンノヨナリ)、落木正文(ラッキーセブン)などの筆名を使っていたという。尾佐竹の人となりが表れていて興味深い。
*尾佐竹は大正5年7月、名古屋控訴院判事として赴任。沼田頼輔(ぬまた・らいすけ)は紋 章学、考古学者。沼田から贈られた著書への礼状に、名古屋の古書店への皮肉を効かすあたりが尾佐竹の面目躍如といったところ。
| 県は石川県立図書館所蔵本、明は明治大学所蔵本、●は非展示 | ||||
| 明41 | 1908 | 志賀瑣羅誌 | ● | |
| 明42 | 1909 | 海南風俗史(海南叢書3)<編> | ● | |
| 大14.10 | 1925 | 賭博と掏摸の研究 | 総葉社書店 | 明 |
| 大14.12 | 1925 | 維新前後に於ける立憲思想−帝国議会前記 | 文化生活研究会 | 県 |
| 大15.6 | 1926 | 法曹珍話閻魔帳 | 春陽堂 | 明 |
| 大15.7 | 1926 | 明治文化史としての日本陪審史 | 邦光堂書店 | 県 |
| 大15.10 | 1926 | 明治警察裁判史 | 邦光堂書店 | 明 |
| 大15.12 | 1926 | 国際法より観たる幕末外交物語 | 文化生活研究会 | 県 |
| 大15.12 | 1926 | 判事と検事と警察−蒙愚理問答 中止・解散・検束 | 総葉社書店 | 県 |
| 昭2.4 | 1927 | 賭博と掏摸の研究 増訂3版 | 総葉社書店 | 県 |
| 昭3.7 | 1928 | 仮名論とローマ字論(日本ローマ字会パンフレット第3冊) | 日本ローマ字会 | ● |
| 昭4.4 | 1929 | 維新前後における立憲思想−帝国議会史前記 前後編 増訂改版 | 文化生活研究会 | ● |
| 昭4.4 | 1929 | 大岡政談(帝国文庫 第16篇)<校> | 博文館 | 明 |
| 昭4.6 | 1929 | 明治秘史疑獄難獄 | 一元社 | 県 |
| 昭4.7 | 1929 | 夷狄の国へ−幕末遣外使節物語 | 万里閣書房 | 県 |
| 昭4.10 | 1929 | 維新前後に於ける立憲思想 後編 | 邦光堂 | ● |
| 昭4.11 | 1929 | 掏摸・賭博(近代犯罪科学全集第9編 売淫・掏摸・賭博) | 武侠社 | 県 |
| 昭5.3 | 1930 | 国際法より観たる幕末外交物語 | 邦光堂 | 明 |
| 昭5 | 1930 | 近世文化史上に於ける大隈重信侯(文明協会ライブラリー) | 文明協会 | ● |
| 昭5.6 | 1930 | 日本憲政史(現代政治学全集第6巻) | 日本評論社 | 県 |
| 昭6.11 | 1931 | 明治大学創立満五十年記念論文集 法学篇(法律論叢10・11)<編> | 明治大学 | 明 |
| 昭7.12 | 1932 | 近世日本の国際観念の発達(現代史学大系第5巻) | 共立社書店 | 明 |
| 昭7.12 | 1932 | 近世日本の国際観念の発達 | 共立社 | 県 |
| 昭8.1 | 1933 | 万国公法と明治維新(使命会後援集 第6輯) | 使命会本部 | 明 |
| 昭8.4 | 1933 | 賭博と掏摸の研究 | 総葉社書店 | 明 |
| 昭8.9 | 1933 | 政党の発達(岩波講座 日本歴史) | 岩波書店 | 県 |
| 昭9.7 | 1934 | 明治文化叢説 | 学芸社 | 明 |
| 昭9.9 | 1934 | 維新前後に於ける立憲思想の研究 | 中文館 | 県 |
| 昭9.9 | 1934 | 秘書類纂 法制関係資料上下<校> | 秘書類纂刊行会 | ● |
| 昭9.10 | 1934 | 掏摸・賭博 | 犯罪科学書刊行会 | 明 |
| 昭9.11 | 1934 | 刑罪珍書解題 | 犯罪科学書刊行会 | 明 |
| 昭10.6 | 1935 | 玄人の玄人・素人の素人らしからざる法律論 | 大誠堂 | 県 |
| 昭10.10 | 1935 | 維新史叢説 | 学而書院 | 県 |
| 昭10.11 | 1935 | 幕末維新の人物 | 学而書院 | 県 |
| 昭11.6 | 1936 | 類聚傅記大日本史 第11巻 政治家篇<編・解説> | 雄山閣 | 明 |
| 昭12.9 | 1937 | 日本憲政史論集(日本政治・経済研究叢書4) | 育生社 | 県 |
| 昭12.9 | 1937 | 法窓秘聞 | 育生社 | 県 |
| 昭13.2 | 1938 | 明治政治史点描(日本政治・経済研究叢書8) | 育生社 | 県 |
| 昭13.2 | 1938 | 日本憲法制定史要 | 育生社 | ● |
| 昭13.11 | 1938 | 日本憲政史大綱 上巻 | 日本評論社 | ● |
| 昭14.1 | 1939 | 日本憲政史大綱 下巻 | 日本評論社 | ● |
| 昭15.10 | 1940 | 新聞雑誌の創始者柳河春三(高山叢書1) | 高山書院 | 明 |
| 昭16.5 | 1941 | 喜寿祝賀会記念石井研堂先生著作目録 附略年譜<編> | 尾佐竹猛 | 明 |
| 昭17.11 | 1942 | 明治維新 上巻(近代日本歴史講座) | 白揚社 | 県 |
| 昭18.4 | 1943 | 明治維新 中巻(近代日本歴史講座) | 白揚社 | 県 |
| 昭18.5 | 1943 | 日本憲政史の研究 | 一元社 | 県 |
| 昭18.8 | 1943 | 明治大正政治史講話 | 一元社 | 県 |
| 昭19.3 | 1944 | 明治の行幸 | 東興社 | 県 |
| 昭19.3 | 1944 | 明治文化の新研究<編> | 亜細亜書房 | 県 |
| 昭19.4 | 1944 | 明治維新 下巻ノ1(近代日本歴史講座) | 白揚社 | ● |
| 昭19.7 | 1944 | 幕末外交秘史考 | 邦光堂書店 | 県 |
| 昭21.9 | 1946 | 明治維新 中巻 重版(近代日本歴史講座) | 白揚書館 | 明 |
| 昭21.10 | 1946 | 明治維新 下巻ノ1 重版(近代日本歴史講座) | 白揚書館 | 明 |
| 昭21.12 | 1946 | 明治維新 上巻 重版(近代日本歴史講座) | 白揚社 | 明 |
| 昭23.10 | 1948 | 賭博と掏摸の研究(尾佐竹猛全集第13巻) | 実業之友社 | 明 |
| 昭23.10 | 1948 | 維新前後の於ける立憲思想(尾佐竹猛全集第1巻) | 実業之友社 | 明 |
| 昭23.11 | 1948 | 幕末遣外使節物語(尾佐竹猛全集第7巻) | 実業之友社 | 明 |
| 昭23.12 | 1948 | 明治秘史疑獄難獄(尾佐竹猛全集第11巻) | 実業之友社 | 明 |
| 昭24.3 | 1949 | 法窓秘聞(尾佐竹猛全集第12巻) | 実業之友社 | 明 |
| 昭24.8 | 1949 | 明治維新 下ノ2(近代日本歴史講座) | 白揚社 | ● |
| 昭26.6 | 1951 | 湖南事件−露国皇太子大津遭難(岩波新書 青版68) | 岩波書店 | 県 |
| 昭44.11 | 1969 | 賭博と掏摸の研究 | 新泉社 | 明 |
| 昭45.10 | 1970 | 志賀瑣羅誌 復刻版 | 高浜町文化財調査委員会 | 明 |
| 昭47.11 | 1972 | 犯姦集録(史談叢書3) | 三崎書房 | 県 |
| 昭53.4 | 1978 | 明治維新 上巻 | 宗高書房 | 県 |
| 昭53.4 | 1978 | 明治維新 下巻 | 宗高書房 | 県 |
| 昭53.9 | 1978 | 日本憲政史大綱 上 | 宗高書房 | 県 |
| 昭53.9 | 1978 | 日本憲政史大綱 下 | 宗高書房 | 県 |
| 昭54.3 | 1979 | 日本憲政史論集 復刻版 | 宗高書房 | ● |
| 昭55.1 | 1980 | 賭博と掏摸の研究 新装版 | 新泉社 | 明 |
| 昭56.6 | 1981 | 類聚傅記大日本史 第11巻 政治家篇<編・解説> 復刻版 | 雄山閣出版 | 明 |
| 昭57.3 | 1982 | 江戸時代犯罪・刑罰事例集<編・解題> | 柏書房 | 明 |
| 昭60.4 | 1985 | 新聞雑誌の創始者柳河春三(近代日本学芸資料叢書 第9輯) | 湖北社 | 明 |
| 平1.12 | 1989 | 幕末遣外使節物語 夷狄の国へ(講談社学術文庫907) | 講談社 | 明 |
| 平3.4 | 1991 | 大津事件−ロシア皇太子大津遭難(岩波文庫 青182-1) | 岩波書店 | 県 |
| 平8.3 | 1996 | スリのテクノロジー | 青弓社 | 県 |
| 平10.12 | 1998 | 明治秘史疑獄難獄 復刻版 | 批評社 | 明 |
| 平11.1 | 1999 | 法曹珍話閻魔帳 復刻版 | 批評社 | 明 |
| 平11.3 | 1999 | 賭博と掏摸の研究 新版 | 新泉社 | 明 |
| 平11.5 | 1999 | 下等百科辞典 | 批評社 | 明 |
| 平11.9 | 1999 | 明治四年賎称廃止布告の研究 | 批評社 | 県 |
| 平11.12 | 1999 | 法窓秘聞 | 批評社 | 県 |
| 本リストは田熊渭津子編『尾佐竹猛(人物書誌大系)』を参考に石川県立図書館及び明治大学図書館の蔵書によって補訂した。 | ||||